天香茶行 石鎖雲(武夷岩茶・烏龍茶)30g 中国茶
1,400
福建省武夷山の岩茶。正岩と呼ばれる限られた地域で作られた伝統的な高級烏龍茶。
福建省の武夷岩茶
武夷岩茶(ぶいがんちゃ)という名前は聞いたことがある方が多いのではないでしょうか。福建省にある武夷山はお茶の歴史の中で非常に重要な場所です。その歴史は古く商の暴君・紂王を討つべく後の周の武王が立ち上がった際、濮みん(門の中に虫)族の長がその茶を献上したという伝説的なものから、唐の時代には孫樵という人の文章に初めて文字としての記載が見られ、さらに元の時代からは正式に貢茶としての地位を獲得します。烏龍茶の発祥にも説がありますが、明末清初、安溪の人が武夷山の製茶法を参考に生み出したと言われており、今でも安溪の鉄観音、武夷山の岩茶は中国を代表する烏龍茶です。台湾の凍頂烏龍茶の由来はこの武夷山の茶樹ですし、また紅茶の発祥地も武夷山であると考えられています。
現在、岩茶は国家標準に定めがあり、名岩産区と丹岩産区で産出するもので、伝統的な製茶方法を用い、岩韵(岩骨花香)と呼ばれる香味を持った烏龍茶が岩茶と呼ばれます。名岩区は本来の岩茶の産地で約70平方キロメートル、丹岩区はその周囲約2800平方キロメートルで、名岩区の中でも特に環境の良いエリアの茶は正岩と呼ばれます。この辺りは観光地としても名高く、三十六峰、七十二洞、九十九岩があるといわれ、曲がりくねった渓谷が続く奇観の地、気候は温和で雨量が多く茶葉の栽培に適しています。盆栽式茶園などと言われる狭い範囲に茶樹があり、「岩岩有茶、非岩不茶」という言葉が岩茶という名の由来です。狭いエリアごとに茶の名前が違うので千を超える岩茶があるそうです。
こちらの石鎖雲は、正岩にあたる碧石区の岩茶。樹齢30年以上の均質に揃った茶樹の葉を用い、伝統技法にのっとった炭培と呼ばれる焙煎を施した高級岩茶です。
※中国茶早わかり
中国茶をあまり知らない方のため、当店で商品をお買い上げの方すべてに中国式のお茶の淹れ方や茶器を紹介したリーフレットを同封しています。はじめての方や贈り物にされる方もご安心ください。


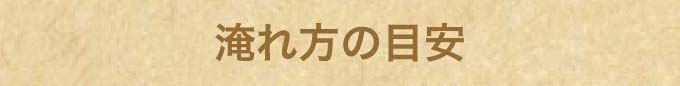
| 湯温度 | 100度 |
| 茶葉の量 | 4g(湯100ml) |
| 抽出時間 | 1回目 30秒 以降+10秒 2回目40秒、3回目50秒と10秒程度ずつ長くしていくのがおすすめの淹れ方です。5、6回はおいしく飲むことができます。味の変化もお楽しみください。 |
