北海シマエビ(500g)×1個(L・30〜40尾前後)北海道産
9,800
締りの良い身に抜群の旨味を秘めた北海シマエビは、北海道を代表する味覚です。
漁獲量が少ないため、北海道以外ではほとんど出回りません。
ゆでたての北海シマエビは、とても香りが良く、締まりの良い身には、次から次へと何度でも手が出てしまうほどの濃い旨みがあります。
【商品内容】
◆北海シマエビ 500g(30〜40尾前後)
※産地によって、「L」または「中」とサイズ表示されています。
【生産地】北海道(主に厚岸湾、サロマ湖、標津、根室沿岸、釧路町)
【発送期間】在庫が無くなり次第販売を終了します。
(新物は9月上旬から出荷を開始します。)
【冷凍配送】
【賞味期限】 別途、商品に記載。(製造日から180日)
漁獲量が少ないため、北海道以外ではほとんど出回りません。
ゆでたての北海シマエビは、とても香りが良く、締まりの良い身には、次から次へと何度でも手が出てしまうほどの濃い旨みがあります。
【商品内容】
◆北海シマエビ 500g(30〜40尾前後)
※産地によって、「L」または「中」とサイズ表示されています。
【生産地】北海道(主に厚岸湾、サロマ湖、標津、根室沿岸、釧路町)
【発送期間】在庫が無くなり次第販売を終了します。
(新物は9月上旬から出荷を開始します。)
【冷凍配送】
【賞味期限】 別途、商品に記載。(製造日から180日)


北海道東部沿岸の、アマモが生い茂る浅い海に生息する北海シマエビは、漁獲量が少ないため、北海道内の鮮魚店でも見かける機会の少ない希少なエビです。 その多くの同属種が、深海に生息するタラバエビ科に属しますが、北海シマエビは、浅瀬に生息しています。 |  獲れたばかりの北海シマエビは緑茶色 |

アマモが生い茂る浅い海に生息する北海シマエビ
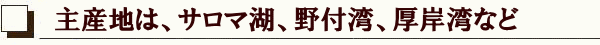
 ゆでると赤い縞模様が美しい北海シマエビ | 殻に縞模様が入っているため、「北海シマエビ」の名で呼ばれますが、正式和名は、「ホッカイエビ」といいます。 主産地は、サロマ湖、野付湾、厚岸湾などで、漁は夏漁と秋漁に分けて行われます。 夏漁が開始されると、北海シマエビの冷蔵出荷が行われますが、消費期限が短いため、当店では、冷凍エビの出荷が始まる7月中旬から、新物の発送を開始しています。 |

北海シマエビ、ウニ、かき貝、ほたて貝など、豊かな水産物を育てるサロマ湖
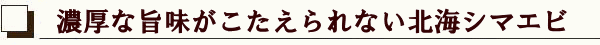
旬は7月から晩秋までの間で、新鮮なものを茹でて出荷しますが、体内に食べた餌が残っていると、その部分が黒ずむため、サロマ湖の漁協などでは、漁獲した北海シマエビを、一時蓄養してから茹でて出荷しています。 ゆでたての北海シマエビは、とても香りが良く、締まりの良い身には、次から次へと何度でも手が出てしまうほどの濃い旨みがあります。 |  締まりの良い身には濃い旨みがあります |
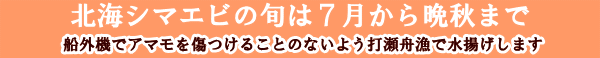
 打瀬舟漁は北海道遺産にも登録されています | 漁が始まると、オホーツク海に面する尾岱沼(海水湖)では、船外機(スクリュー)を止めて、白い帆をかけた磯舟が、湾内を漂いながら漁(打瀬舟(うたせぶね)漁)をする光景が見られます。 これは、船外機でアマモを傷つけないようにするためと、貴重な資源を乱獲から守るために行っている漁法です。 漁は、晩秋の11月上旬まで続きます。 |

