超久 大吟醸酒 720ml 和歌山 中野BC
2,750
目指す酒造りは「究極の食中酒」地元和歌山で「長く久しく愛される酒でありたい」という先代の想いがこもった銘柄「長久」。「超久」はその長久を超える酒を目指して醸しました。新たに武田杜氏を迎え入れ生み出された「超久 大吟醸」。杜氏が自信を持って醸すアルコール添加の技をいかんなく発揮した特別な1本。食事との相性は濃い味付けのものや魚介、白身魚の刺身などとの相性が良いお酒です。冷や、常温、人肌燗で。大吟醸酒なので冷やすのもオススメ。
■商品名:超久 大吟醸 生原酒
■原材料:米(兵庫県産山田錦100%)・米こうじ・醸造アルコール
■日本酒度:+2.0
■アルコール度:18度
■生産地:和歌山県海南市
■内容量:720ml
■生産者:中野BC
※こちらの商品は要冷蔵となります。チルドゆうパックでのお届けになります。
チルド代は送料に含まれています。
■商品名:超久 大吟醸 生原酒
■原材料:米(兵庫県産山田錦100%)・米こうじ・醸造アルコール
■日本酒度:+2.0
■アルコール度:18度
■生産地:和歌山県海南市
■内容量:720ml
■生産者:中野BC
※こちらの商品は要冷蔵となります。チルドゆうパックでのお届けになります。
チルド代は送料に含まれています。
中野BC株式会社 和歌山県海南市

1949年に「中野醸造工場」として創業。それ以前には創業者、中野利生が「中野醤油店」としてここ海南市で醤油醸造を行っていました。他社に類を見ない蒸熟法「大豆蒸熟法」の開発により品質の向上と製造の合理化に成功、関西初のうすくち醤油醸造で163蔵中県下3位の醤油蔵となりました。中野醸造として現在の場所に蔵を構えてからは、甲類焼酎の製造を始め、「富士白」を販売。粗悪な焼酎が出回っていた戦後の時代に、品質にこだわった富士白はたちまち評判を呼び、3年で販売数が県下最大規模に。それを機に焼酎製造に専念するため、醤油製造から撤退しました。
そして富士白の販売からおよそ10年、1958年には「中野酒造株式会社」に改称し、県下62番目の造り酒屋として清酒「長久」を商品化。当初は「焼酎屋の清酒なんて」と敬遠されましたが、試飲会を重ねながら地道に理解を深めていった結果、その品質を認められ、20年で県内出荷数1位になりました。その後も銘柄を増やし、1988年には酒造りのノウハウを蓄積すると共に品質を守り、さらに磨いていくため、蔵人の派遣制をやめ、全国に先駆けて社員蔵人制を導入。日本にその名を轟かす大商人の名を戴いた純米酒「紀伊国屋文左衛門」は、世界最大規模の酒類品評会IWC(インターナショナル ワイン チャレンジ)2011にて金賞を受賞しています。


1979年には梅どころ和歌山の立地を生かして梅酒の開発にも乗り出し、梅酒専門の杜氏を設けて紀州南高梅を使った高品質な商品を展開。1990年にモンドセレクション世界食品品質コンクールにおいて「梅酒」が金賞を受賞、2007年には大阪で行われる天満天神梅酒大会で太陽の光で紅く染まった希少価値の高い梅のみを使った「紀州梅酒 紅南高」が初代グランプリに選ばれました。
1998年より機能性食品の販売・製造を開始し、アルコール製品だけでなく梅エキスなどの和歌山県特産品を原料とした健康食品やエッセンシャルオイル、化粧品などの研究・開発も始まり、2002年に社名を現在の「中野BC株式会社」に変更しました。中野BCのBCとは「Biochemical Creation=生化学の創造」を意味しています。創業から一貫して守られてきた「品質第一」「創意工夫」の伝統。事業の柱となる酒造部門をはじめ、ヘルスケア部門、うめ原料部門、観光部門、研究部門の各部門でその信念を受け継ぎ「衆知をもって常に創造せよ」という企業理念の言葉を胸に、日々研究、開発に力を注いでいます。

超久 大吟醸 生原酒

目指す酒造りは「究極の食中酒」地元和歌山で「長く久しく愛される酒でありたい」という先代の想いがこもった銘柄「長久」。「超久」はその長久を超える酒を目指して醸しました。新たに武田杜氏を迎え入れ生み出された「超久 大吟醸」。杜氏が自信を持って醸すアルコール添加の技をいかんなく発揮した特別な1本。食事との相性は濃い味付けのものや魚介、白身魚の刺身などとの相性が良いお酒です。冷や、常温、人肌燗で。大吟醸酒なので冷やすのもオススメ。
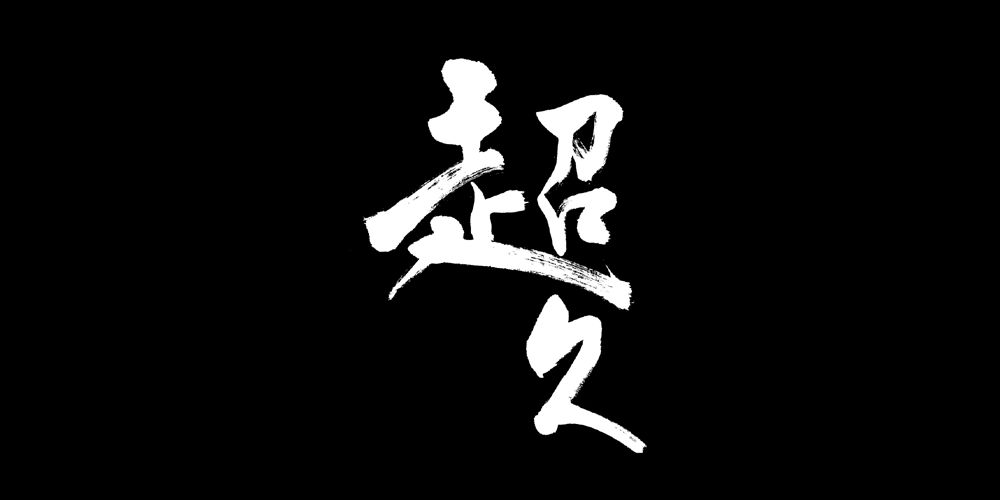
目指す酒造りは「究極の食中酒」
地元和歌山で「長く久しく愛される酒でありたい」
という先代の想いがこもった銘柄「長久」。
「超久」はその長久を"超える酒"を目指して醸しました。

武田杜氏の酒造りに込める想い
古来より日本酒は神事や「ハレ」の日に飲まれていた貴重なお米から出来た神聖なるものです。
それが、民衆にも広がり食卓にもならぶ食中酒としての位置を確立してきました。
日本酒は生活の一部であり、食事を通してどんなお酒がいいのだろうと日々考えています。
「文化」を守り、中野BCらしい「米の旨味」をベースにした、後味のキレイなお酒・・・
自分に合ったお気に入りの日本酒を見つけてもらえるように、
また、皆様の生活に寄り添えるような幅広い種類の日本酒を造っていきたいです。
