舞踊刀 剣舞刀 踊り 刀 脇差し 小太刀 日本刀 模造刀 小道具 お稽古用 74cm
お稽古用の舞踊刀です。歌舞伎や日舞のお稽古用、寸劇やお芝居・コント等でご利用ください。本商品のように、刀の中でも比較的短めのものを脇差し「わきざし」と呼ぶ場合があります。
鍔「つば」や柄「つか」の頭「かしら」・縁「ふち」、目貫「めぬき」や刃文「はもん」等は簡略化してありますので、本格的な時代劇や舞台ステージには不向きです。
※刃は付いておりませんが、ジュラルミン製の刀身は相当に鋭利ですので取り扱いには十分ご注意ください。模造刀ですので登録は不要です。同じデザインの舞踊刀(稽古用脇差し/全長52cm)もございます。
■素材
鞘「さや」:木製漆塗り
柄「つか」:プラスティック製に柄巻「つかまき」
鍔「つば」:アルミ
刀身:ジュラルミン(アルミ合金)
■サイズ
全長:74センチ
刃渡り:47センチ
■重さ
300グラム
■色
鞘「さや」:黒
柄「つか」:黒
刀身:シルバー
| ■商品説明 | お稽古用の舞踊刀です。歌舞伎や日舞のお稽古用、寸劇やお芝居・コント等でご利用ください。本商品のように、刀の中でも比較的短めのものを脇差し「わきざし」と呼ぶ場合があります。
鍔「つば」や柄「つか」の頭「かしら」・縁「ふち」、目貫「めぬき」や刃文「はもん」等は簡略化してありますので、本格的な時代劇や舞台ステージには不向きです。
※刃は付いておりませんが、ジュラルミン製の刀身は相当に鋭利ですので取り扱いには十分ご注意ください。模造刀ですので登録は不要です。同じデザインの舞踊刀(稽古用脇差し/全長52cm)もございます。 | | ■素材 | 鞘「さや」:木製漆塗り
柄「つか」:プラスティック製に柄巻「つかまき」
鍔「つば」:アルミ
刀身:ジュラルミン(アルミ合金) | | ■サイズ | 全長:74センチ
刃渡り:47センチ | | ■重さ | 300グラム | | ■色 | 鞘「さや」:黒
柄「つか」:黒
刀身:シルバー | | ■備考 | 【形状による刀の分類】
打刀 「うちがたな」
反りのある刀身を持ち、柄や鍔、切羽など複数の部品で構成される、一般的な形状の日本刀。単純に「日本刀」と言った場合、打刀を指す事が多い。現代の分類では、刃長(切っ先から棟区までの直線距離)60cm以上のものを指し、60cm未満のものは脇差と呼ぶ。
太刀「たち」
構造は打刀と殆ど同じだが、携帯方法が大きく違い(打刀は刃を上にし帯に差して携帯するのに対し、太刀刃を下にし吊るして携帯する)、それに伴い拵(外装)も異なる。又、柄や鞘の装飾が凝らしてある物も多い。現代の分類では刃長60cm以上のものを指し、60cm未満のものは脇差と呼ぶ。前述してあるように刀身のみを見比べれば大きな違いはないが、全般的にそりが深いのが特徴である。
脇差(脇指)「わきざし」
刀身の短い打刀(太刀)。現代の分類では、刃長30cm以上60cm未満のものを指す。脇差の中でも60cmに近い刃長を持つものを特に小太刀または長脇差と呼ぶ。
大太刀「おおたち」
長大な刀身を持つ打刀(太刀)。野太刀とも言う。現代の分類では、刃長が90cm以上のものを指す。腰に差す(吊るす)には長すぎる為、背負うか担ぐかして携帯された。使い方は重量に任せて馬上から叩っ斬るのが一般的。
毛抜形太刀「けぬきがたたち」
茎(なかご)が柄(つか)の役割を兼ねている太刀。直刀から湾刀への過渡期に存在する。
小烏丸形太刀「こがらすまるがたたち」
刃区から物打辺りまで鎬造り(しのぎづくり)であるが、切先が両刃造りに似ている。反りも少し有る。直刀から湾刀への過渡期に存在する。
短刀「たんとう」
現代の分類では、刃長30cm未満のものをいう。ただし、30cm以上であっても反りのほとんどない平造りのものなどは「寸延び」などといい短刀に含める場合がある。
長巻「ながまき」
ほぼ刀身と同じ長さの柄を持つ大太刀。大太刀の柄を延長して取り回し易くした「中巻き」から発展したもの。長巻と中巻きの違いは、最初から柄を長く作ってあるか、通常の大太刀の柄を延長して長くしたものか、の違い。正倉院内に原型らしき長柄武器が残っている。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より | |
|
| 舞踊刀(稽古用脇差し/全長74cm)−寸劇用小太刀 |
 |
|
| 柄「つか」 |
 |
|
| 鍔「つば」 |
 |
|
| 切っ先(きっさき)・鞘「さや」 |
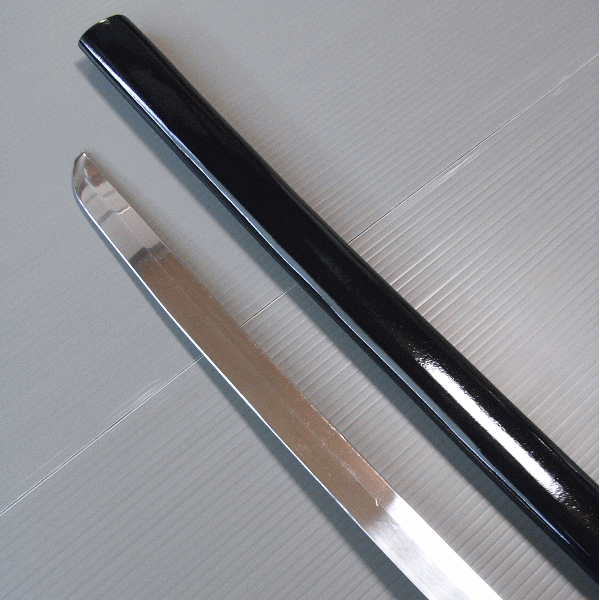 |
|
[関連商品キーワード]
舞踊刀 全長74cm お稽古用脇差し 寸劇用小太刀 舞踊小道具 ステージ用刀 舞台用刀 寸劇用刀 踊り小道具 kz
