桜 盆栽 さくら サクラ しだれ桜 枝垂桜 シダレ ミニ盆栽 ギフト プレゼント 誕生日 結婚記念日 お供え 卒業 入学 送料無料 鉢植え 花ギフト
6,580
桜 盆栽 さくら サクラ しだれ桜 枝垂桜 シダレザクラ ミニ盆栽 ギフト プレゼント 誕生日 結婚記念日 お供え 卒業 入学 送別 陶器鉢 送料無料 鉢植え 苗木 さくら 室内 しだれ桜 桜の木 おしゃれ 盆栽鉢 小品盆栽 啓翁桜 花 花ギフト
| しだれ桜の鉢植えギフト | |||||||||||||
 枝垂れ桜(シダレザクラ)の特徴 | |||||||||||||
 枝垂れ桜(シダレザクラ)の栽培環境 | |||||||||||||
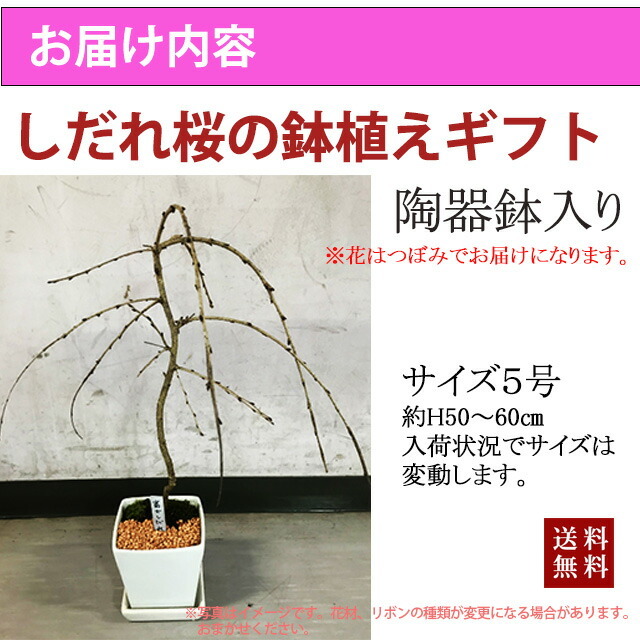 しだれ桜の発送は2月上旬〜3月頃まで、無くなり次第終了です。 しだれ桜の花言葉 | |||||||||||||
 | |||||||||||||
| |||||||||||||
 | |||||||||||||
 | |||||||||||||
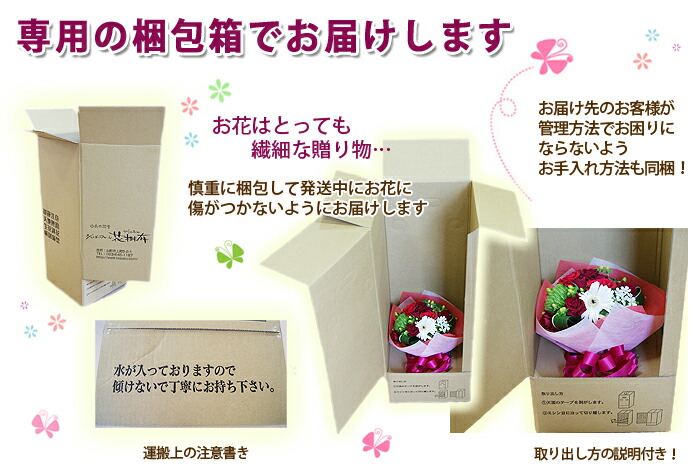 | |||||||||||||
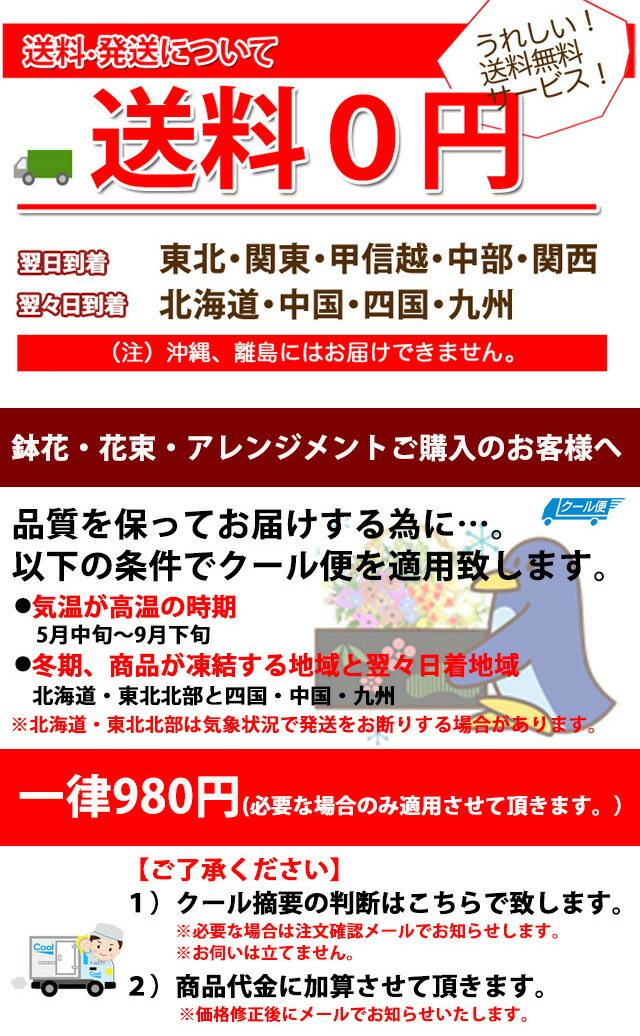 | |||||||||||||
 | |||||||||||||
 しだれ桜の発送は2月上旬〜3月頃まで、無くなり次第終了です。 |




