茶道具 茶杓 上 白竹又は古竹(染竹風)又は煤竹 奈良高山製 紙箱入 茶道
3,300
●メール便不可
上茶杓 白竹又は古竹(染付風)又は煤竹<br>
生産地:国産(奈良高山製)
箱:紙箱
注意:特に古竹:染竹は色・景色(模様)などは写真と異なる場合があります。
備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)
上茶杓 白竹又は古竹(染付風)又は煤竹<br>
生産地:国産(奈良高山製)
箱:紙箱
注意:特に古竹:染竹は色・景色(模様)などは写真と異なる場合があります。
備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)
谷村弥三郎作(翠華園)
通産大臣指定伝統工芸師
奈良高山製
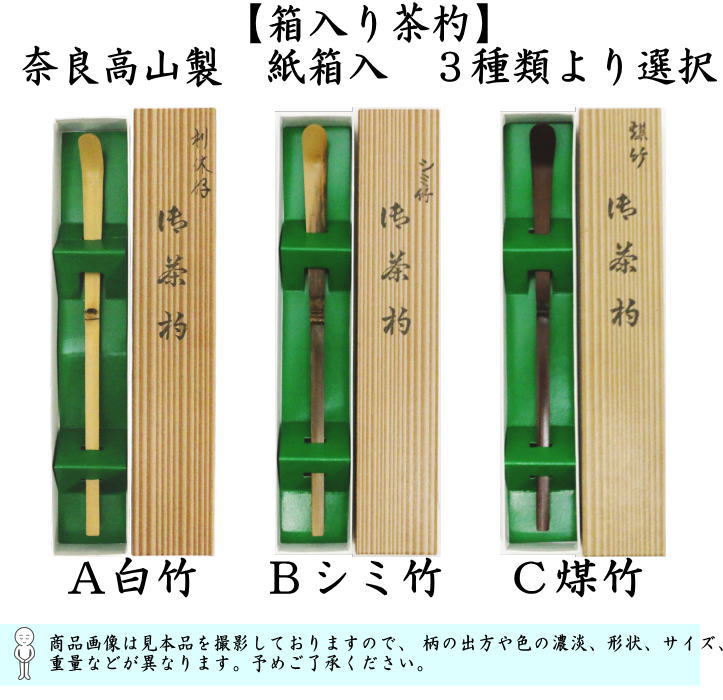 |





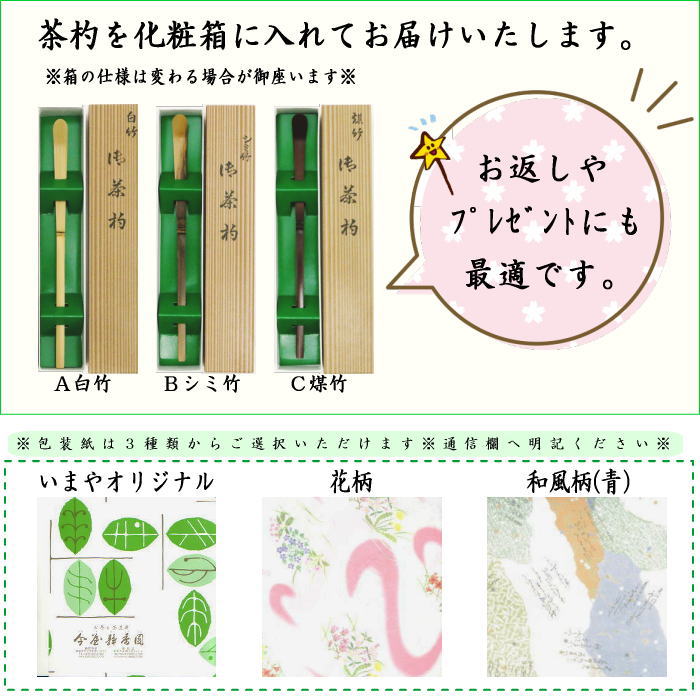
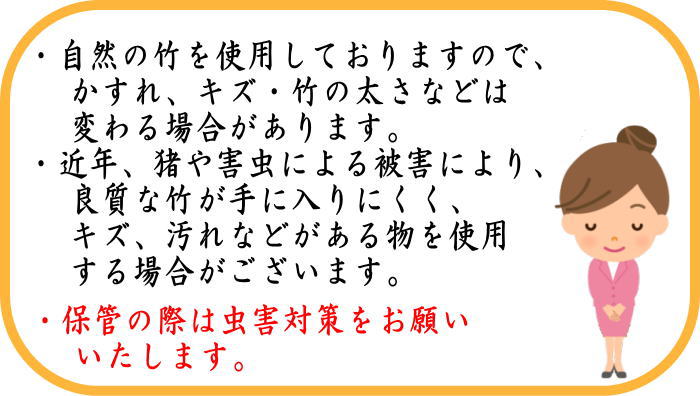
【茶杓削り】
【京都工芸研究会 高野宗陵作(高野忠男) 】
茶杓(利休型)の主な制作手順を示します。(「茶杓教室テキスト」(高野竹工株式会社)より)
(材料の準備1)竹を油抜きし乾燥させる。
↓
(材料の準備2)茶杓の寸法にあわせて,材料を切り出す。
↓
(材料の準備3)水につけ繊維を柔らかくしてから,ローソクの火で櫂先となる部分をまげる。
↓
1:茶杓の全長:鉛筆で182ミリの箇所に印をつけ,印のところで切断する。
2:櫂先を幅11ミリ程度になるまで削る。
3:茶杓を逆手に持ち,ヨウ(裏側部分)から表皮に向けて削り,節で止める。
これを繰り返し,節の位置で幅8ミリに仕上げる。
4:おっとりを持ち,反対側を3と同様に節まで削る。節に残った屑は削り取る。
5:おっとり部分をナイフで削り,幅7ミリに仕上げる。
6:3〜5を数度繰り返して形を作る。
7:櫂先を削り丸くする。ヨウを削り,切っ先を薄く仕上げる。
8:裏側の角をナイフで削り取る。
9:サンドペーパー等で角を丸くして形を整える。
10:切止。ナイフで一気に行う。完成。
