茶道具 茶筌 茶筅 茶せん 真数穂 真茶筅 谷村丹後作 奈良高山製 茶道
7,480
【茶筅の国産製と海外製の違い】
・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。
海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。
・製造方法にも違いがあります。
味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。
やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。
----------
作者:谷村丹後作(和北堂)
(通産大臣指定伝統工芸師)
----------
室町時代後期に、大和鷹山の城主鷹山大膳介頼栄の次男であった鷹山宗砌が、連歌を通じ親交のあった、当時の奈良称名寺住職、村田珠光のアドバイスを得て、茶筅を創案したと伝えられています。
【19代 谷村丹後】(和北堂)伝統工芸士
裏千家出入方の茶筅師
昭和07年1月30日生れ
日本職人名工会 殿堂名匠
【20代 谷村丹後(谷村淳)】
現在、次代も製作・研鑽中
----------
素材:奈良高山製品
箱:化粧箱
・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。
海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。
・製造方法にも違いがあります。
味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。
やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。
----------
作者:谷村丹後作(和北堂)
(通産大臣指定伝統工芸師)
----------
室町時代後期に、大和鷹山の城主鷹山大膳介頼栄の次男であった鷹山宗砌が、連歌を通じ親交のあった、当時の奈良称名寺住職、村田珠光のアドバイスを得て、茶筅を創案したと伝えられています。
【19代 谷村丹後】(和北堂)伝統工芸士
裏千家出入方の茶筅師
昭和07年1月30日生れ
日本職人名工会 殿堂名匠
【20代 谷村丹後(谷村淳)】
現在、次代も製作・研鑽中
----------
素材:奈良高山製品
箱:化粧箱
 |

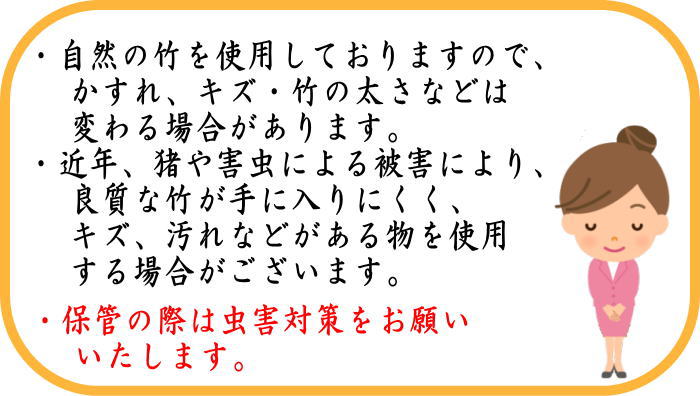
【茶筅の国産製と海外製の違い】
・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。
海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。
・製造方法にも違いがあります。
味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。
やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。
【谷村丹後】(和北堂)
室町時代後期に、大和鷹山の城主鷹山大膳介頼栄の次男であった鷹山宗砌が、連歌を通じ親交のあった、当時の奈良称名寺住職、村田珠光のアドバイスを得て、茶筅を創案したと伝えられています。
その茶筅作りの技法を、鷹山家の家臣に伝授し、鷹山家没落後、地名も『鷹山』から『高山』に改まり、茶筅作りが生業となりました。
その後茶道の隆盛と共に需要も高まり、豊臣秀吉や徳川幕府によって保護産業として優遇され、当家におきましては、徳川将軍家御用茶筅師として『丹後』の名が記録され、将軍家以外にも禁裏仙洞御所や、公家、諸大名への納入の際に使用された『何々御用』と書かれた木札や提灯箱が残されています。
16世紀には幕府より官許があり、1716年には京都 所司代より先人である丹後も含め13人に苗字帯刀が許されます。
今も、 一子相伝の制度を継承しております。
【19代 谷村丹後】(和北堂)伝統工芸士
裏千家出入方の茶筅師
1932年昭和07年1月30日生れ
日本職人名工会 殿堂名匠
【20代 谷村丹後(谷村淳)】
現在、次代も製作・研鑽中
【茶筅の国産製と海外製の違い】
・国産は国内産の淡竹(はちく)を使用し、竹を冬期間に刈り取り、1年以上寝かせて、乾燥させて製品化します。
海外製の物は、乾燥させていないため、防腐剤、防カビ剤などが使用されていることがあります。
・製造方法にも違いがあります。
味削り(茶筅の穂先を薄く削っていく工程)を国産の茶筅は、職人が一本ずつ、小刀でそぐように薄くしていきますが、海外では、味削りをやすりで行います。
やすりで削るほうが、簡単で早くできますが、穂先の表面に細かい傷が残るため、穂先が折れやすくなります。
----------
作者:谷村丹後作(和北堂)
(通産大臣指定伝統工芸師)
----------
室町時代後期に、大和鷹山の城主鷹山大膳介頼栄の次男であった鷹山宗砌が、連歌を通じ親交のあった、当時の奈良称名寺住職、村田珠光のアドバイスを得て、茶筅を創案したと伝えられています。
【19代 谷村丹後】(和北堂)伝統工芸士
裏千家出入方の茶筅師
昭和07年1月30日生れ
日本職人名工会 殿堂名匠
【20代 谷村丹後(谷村淳)】
現在、次代も製作・研鑽中
----------
素材:奈良高山製品
箱:化粧箱
