茶道具 水指 水差し 曲水指 杉木地 利休好写し 国産材使用 利休好写 茶道
29,040
●曲物(まげもの)とは…薄い板材を、輪状に曲げて底をつけた器物のことをいいます。
檜(ひのき)、杉(すぎ)、檜葉(ひば)、椹(さわら)など比較的くせのない材料で薄板を作り、水指や建水などでは湯曲(ゆまげ)といい、熱湯で柔らかくした板を曲げて、薄く帯状にした桜の樹皮などで合わせ目を縫い合わせ、それに底や蓋などを付けます。
●曲水指(まげみずさし)とは…利休好みは、杉の曲で、指渡しが五寸八分、高さ四寸九分、厚み二分、足長さ一寸五分、高さ三分半、綴目二十一、蓋差渡し六寸一分、厚さ一分八厘、掛り二分、高さ五分となっています。
木地曲水指は、炉に用いるものとされ、一会限りの使い切りで、水に濡らし拭い切って使用されていたようです。
綴目と足一つを前にして、蓋は杢目横に蓋裏の綴目は向うになります。
その他、好み物にも曲物だけでなく塗物など、様々なものがあります。
----------
サイズ:約直径17.5×蓋含む高17cm
約蓋直径18.2cm
約蓋除く高15.6cm
素材:杉 国産材使用
箱:化粧箱
備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)
檜(ひのき)、杉(すぎ)、檜葉(ひば)、椹(さわら)など比較的くせのない材料で薄板を作り、水指や建水などでは湯曲(ゆまげ)といい、熱湯で柔らかくした板を曲げて、薄く帯状にした桜の樹皮などで合わせ目を縫い合わせ、それに底や蓋などを付けます。
●曲水指(まげみずさし)とは…利休好みは、杉の曲で、指渡しが五寸八分、高さ四寸九分、厚み二分、足長さ一寸五分、高さ三分半、綴目二十一、蓋差渡し六寸一分、厚さ一分八厘、掛り二分、高さ五分となっています。
木地曲水指は、炉に用いるものとされ、一会限りの使い切りで、水に濡らし拭い切って使用されていたようです。
綴目と足一つを前にして、蓋は杢目横に蓋裏の綴目は向うになります。
その他、好み物にも曲物だけでなく塗物など、様々なものがあります。
----------
サイズ:約直径17.5×蓋含む高17cm
約蓋直径18.2cm
約蓋除く高15.6cm
素材:杉 国産材使用
箱:化粧箱
備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)
 |

曲物(まげもの)とは
薄い板材を、輪状に曲げて底をつけた器物のことをいいます。
檜(ひのき)、杉(すぎ)、檜葉(ひば)、椹(さわら)など比較的くせのない材料で薄板を作り、水指や建水などでは湯曲(ゆまげ)といい、熱湯で柔らかくした板を曲げて、薄く帯状にした桜の樹皮などで合わせ目を縫い合わせ、それに底や蓋などを付けます。
曲水指(まげみずさし)とは
利休好みは、杉の曲で、指渡しが五寸八分、高さ四寸九分、厚み二分、足長さ一寸五分、高さ三分半、綴目二十一、蓋差渡し六寸一分、厚さ一分八厘、掛り二分、高さ五分となっています。
木地曲水指は、炉に用いるものとされ、一会限りの使い切りで、水に濡らし拭い切って使用されていたようです。
綴目と足一つを前にして、蓋は杢目横に蓋裏の綴目は向うになります。
その他、好み物にも曲物だけでなく塗物など、様々なものがあります。
水指(水器)-釜に補給する水や茶碗・茶筌などをすすぐための水を貯えておく器物
炉・風炉の火の陽の対して水指の水を陰とします。
台子皆具の水指は本来唐物に始まり点前作法の変遷とともに皆具からはなれ銅の水指についで南蛮や国焼の備前・信楽・楽焼や京焼などの焼き物が用いられ、さらに木地釣瓶や曲などの新しい素材や形が造られた。

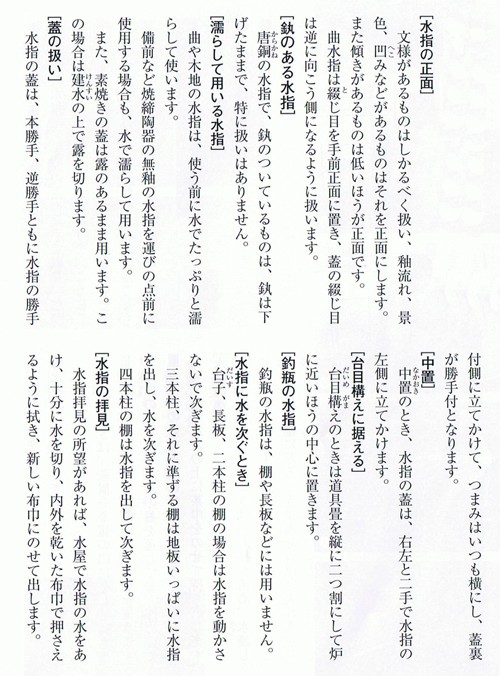
●曲物(まげもの)とは…薄い板材を、輪状に曲げて底をつけた器物のことをいいます。
檜(ひのき)、杉(すぎ)、檜葉(ひば)、椹(さわら)など比較的くせのない材料で薄板を作り、水指や建水などでは湯曲(ゆまげ)といい、熱湯で柔らかくした板を曲げて、薄く帯状にした桜の樹皮などで合わせ目を縫い合わせ、それに底や蓋などを付けます。
●曲水指(まげみずさし)とは…利休好みは、杉の曲で、指渡しが五寸八分、高さ四寸九分、厚み二分、足長さ一寸五分、高さ三分半、綴目二十一、蓋差渡し六寸一分、厚さ一分八厘、掛り二分、高さ五分となっています。
木地曲水指は、炉に用いるものとされ、一会限りの使い切りで、水に濡らし拭い切って使用されていたようです。
綴目と足一つを前にして、蓋は杢目横に蓋裏の綴目は向うになります。
その他、好み物にも曲物だけでなく塗物など、様々なものがあります。
----------
サイズ:約直径17.5×蓋含む高17cm
約蓋直径18.2cm
約蓋除く高15.6cm
素材:杉 国産材使用
箱:化粧箱
備考:在庫ありの場合(注文日〜3日以内の発送可能)
