茶道具 枝炭 7本セット 三ツ又 2本 二ツ又 5本入り 炉用又は風炉用 表千家又は裏千家用兼用 2種類より選択
2,381
●枝炭(えだずみ)とは…亭主が客の前で炉や風炉に炭を組み入れる炭点前(すみでまえ)で用いる、躑躅(ツツジ)などの細い枝が二股・三股になった小枝を焼いたもので、普通はこれに胡粉(貝殻を焼いて作った白色の顔料)を塗り白い色にしたもので、「白炭」(しろずみ)ともいいます。
白く塗らない焼いたままのものを「山色」(やまいろ)といい、武家茶に好まれます。
炭置の景色と、火移りが早いため、導火の役割もしています。
枝が二本のものと三本のものがあり、用い方は流儀により異なります。
元来は「光瀧炭」(こうたきずみ)という、炭を赤熱した状態で窯から引き出し灰をかけて消して作った白い炭を用いていましたが、古田織部が細い躑躅などを焼いて胡粉を塗るようになったといいます。
----------
●特長
・各三つ枝 2本・二つ枝 5本のセットです。
・本物の枝を焼いた物に白い色を塗布しています。
(形などは一点一点異なります)
・壊れやすいので、米殻を挟んで箱に入っています。
----------
入数:三ツ又 2本
二ツ又 5本入
サイズ:炉用(各約長さ18cm)
風炉用(各約長さ15.5cm)
白く塗らない焼いたままのものを「山色」(やまいろ)といい、武家茶に好まれます。
炭置の景色と、火移りが早いため、導火の役割もしています。
枝が二本のものと三本のものがあり、用い方は流儀により異なります。
元来は「光瀧炭」(こうたきずみ)という、炭を赤熱した状態で窯から引き出し灰をかけて消して作った白い炭を用いていましたが、古田織部が細い躑躅などを焼いて胡粉を塗るようになったといいます。
----------
●特長
・各三つ枝 2本・二つ枝 5本のセットです。
・本物の枝を焼いた物に白い色を塗布しています。
(形などは一点一点異なります)
・壊れやすいので、米殻を挟んで箱に入っています。
----------
入数:三ツ又 2本
二ツ又 5本入
サイズ:炉用(各約長さ18cm)
風炉用(各約長さ15.5cm)
 |
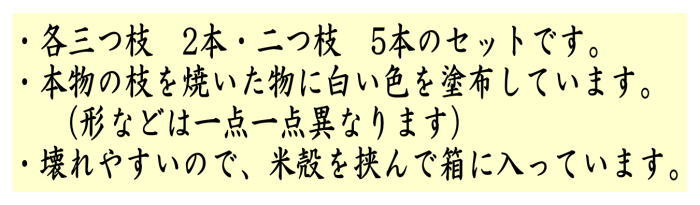
- 枝炭(えだずみ)とは
- 亭主が客の前で炉や風炉に炭を組み入れる炭点前(すみでまえ)で用いる、躑躅(ツツジ)などの細い枝が二股・三股になった小枝を焼いたもので、普通はこれに胡粉(貝殻を焼いて作った白色の顔料)を塗り白い色にしたもので、「白炭」(しろずみ)ともいいます。
白く塗らない焼いたままのものを「山色」(やまいろ)といい、武家茶に好まれます。
炭置の景色と、火移りが早いため、導火の役割もしています。
枝が二本のものと三本のものがあり、用い方は流儀により異なります。
元来は「光瀧炭」(こうたきずみ)という、炭を赤熱した状態で窯から引き出し灰をかけて消して作った白い炭を用いていましたが、古田織部が細い躑躅などを焼いて胡粉を塗るようになったといいます。
