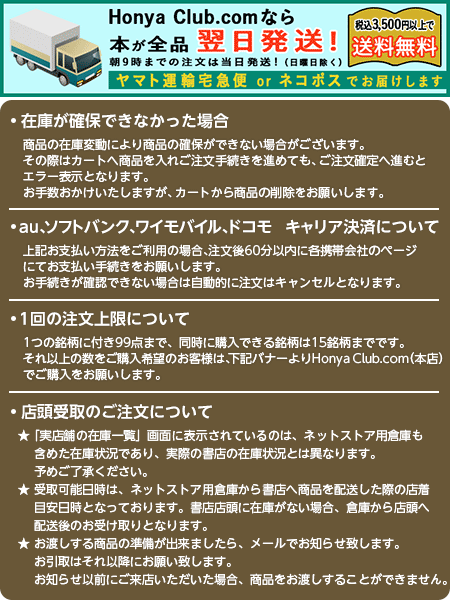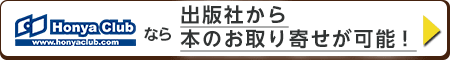翌日発送・生命の農/林真司
2,200
出版社名:みずのわ出版、地方・小出版流通センター
著者名:林真司
発行年月:2020年08月
キーワード:セイメイ ノ ノウ、ハヤシ,シンジ
著者名:林真司
発行年月:2020年08月
キーワード:セイメイ ノ ノウ、ハヤシ,シンジ
内容情報
レイチェル・カーソンが『沈黙の春』で、DDTなど化学薬品による環境汚染を告発したのは、1961年のことである。しかしそれより2年遡る1959年に「農薬の害」を公式に発表し、人体に対する農薬の多大なる悪影響を世に問うたのが、奈良県五條市の開業医・梁瀬義亮(やなせ・ぎりょう、1920-1993)であった。発表当初は、周囲からの誹謗中傷に晒され続けた。しかし諄諄と「無農薬有機農法」の大切さを説く梁瀬の誠実な姿勢に、賛同の輪が各地に広がっていく。
梁瀬は医師として、そして自ら有機農業を実践しながら、生命をないがしろにする社会の在り方に、敢然と異議申し立てを続けた。有吉佐和子は、そんな梁瀬の姿に強い感銘を受け、1970年代半ばベストセラーとなった小説『複合汚染』のなかで詳しく紹介し、最大級の賛辞を贈った。
近年、日本における食の安全性は、高度経済成長期と比べて向上したかに見える。しかし、一皮むけば心許ない状況にあることに変わりはなく、農薬や化学肥料への依存はむしろ強まっている。食品添加物の使用も巧妙になった。だからこそ、小説『複合汚染』が広く支持された1970年代を、いま一度再検証する必要がある。
過去を直視しなければ、未来を語ることができない。梁瀬義亮が警鐘を鳴らし、有吉佐和子が問題提起をした、昭和という「複合汚染」の時代とは、いったい何だったのか。梁瀬が生涯追い求めた「生命の農法」への軌跡を通して、その実像に迫っていく。