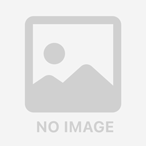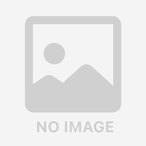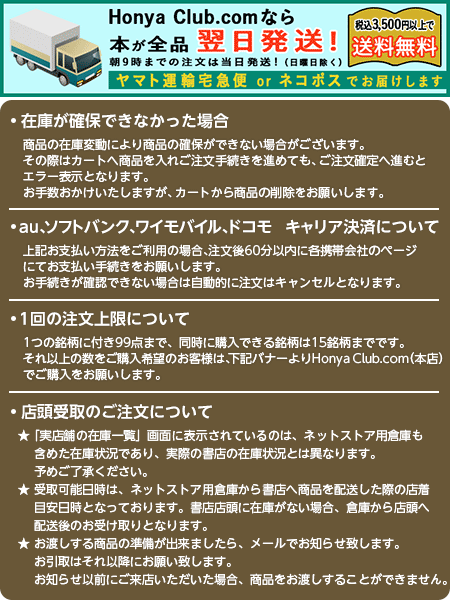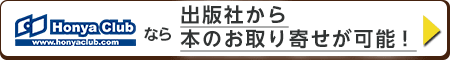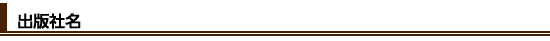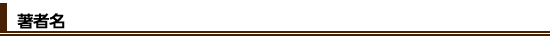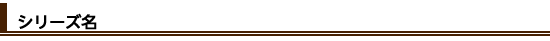翌日発送・碓氷峠の一世紀/三宅俊彦
2,200
出版社名:ネコ・パブリッシング
著者名:三宅俊彦
シリーズ名:RM ReーLibrary
発行年月:2022年12月
キーワード:ウスイ トウゲ ノ イッセイキ、ミヤケ,トシヒコ
著者名:三宅俊彦
シリーズ名:RM ReーLibrary
発行年月:2022年12月
キーワード:ウスイ トウゲ ノ イッセイキ、ミヤケ,トシヒコ
内容情報
既に260号を超える長い歴史の「RM LIBRARY」から、過去の傑作巻を2〜3冊分まとめて復刻する「RM Re-Library(アールエム リ・ライブラリー)」。
シリーズ7巻目は、かつて国鉄線で最大勾配区間であることで知られ、終生特殊な運転方式が取られていた信越本線の碓氷峠区間(横川〜軽井沢)間の歴史を振り返ります。
RMライブラリーの第40・41巻として刊行したもので、さらにカラーグラフ4ページを新規制作しています。
当区間の開業は129年前となる1893年。最急勾配66.7‰、駅間距離11kmあまりで、当初はアプト式と呼ばれるラックレール式が採用されていました。
結局我が国において国鉄/JR線におけるアプト式の採用はこの区間だけであったことから見ても、いかに難区間・難工事であったことかが窺われます。
当初は非電化で開業となりましたが、トンネルの多さ・速度の遅さから来る煙害をなくすべく、1911年に電化。幹線においては初めてとなる電気機関車による運転が開始されました。
長きにわたったアプト式運転でしたが、1963年に通常の粘着式運転に変更し、複線化もなされて輸送力増強がなされました。
とはいえ、専用後押し機関車のEF63形が全列車に連結される必要があり、横川駅での連結・解結シーンは「峠の釜めし」と共に旅の風物詩として多くの方に親しまれました。
1997年の北陸新幹線長野開業でこの在来線の碓氷峠区間が廃止となってからちょうど25年。
本書では1893〜1997年の104年間の歴史を、「運転史」という観点から掘り起こします。興味深い機関車運用から変わった列車、そしてそこで働いた人たちの生活が窺えるエピソードまでが手に取るように伝わります。
著者はこうした運転史に関する第一人者である三宅俊彦さん。さらに多くの貴重な写真・図版類も収録されております。