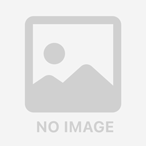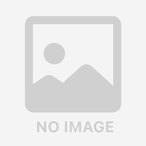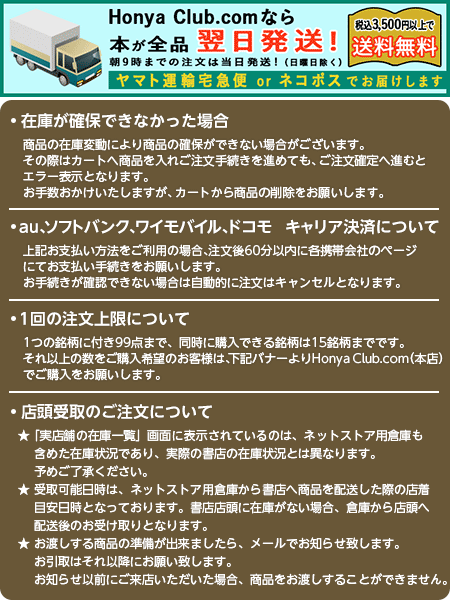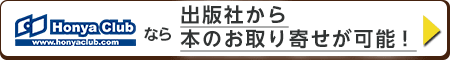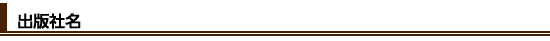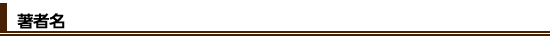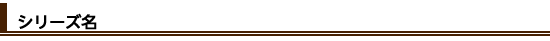翌日発送・気候変動と農業の危機/農政ジャーナリストの
1,320
出版社名:農政ジャーナリストの会、農山漁村文化協会
著者名:農政ジャーナリストの会
シリーズ名:日本農業の動き
発行年月:2025年02月
キーワード:キコウ ヘンドウ ト ノウギョウ ノ キキ、ノウセイ ジャーナリスト ノ カイ
著者名:農政ジャーナリストの会
シリーズ名:日本農業の動き
発行年月:2025年02月
キーワード:キコウ ヘンドウ ト ノウギョウ ノ キキ、ノウセイ ジャーナリスト ノ カイ
内容情報
国連のグテーレス事務総長が「地球沸騰化」と表現する状況下、猛暑や豪雨、干ばつなどの異常気象が頻発し、国内でも幅広い農林水産物に収量・品質の低下など深刻なダメージが出ている。この危機を克服するには、作目転換や生産技術の抜本的な見直しなど大胆な革新を図る必要があることは既に共通認識といってよい。この気候危機と農業の関係について識者の見解を伺った研究会シリーズの記録。
農林中金総合研究所客員研究員で気象予報士の田家康氏は、気候変動がもたらす政治・経済・社会への影響を独自の視点から分析。1次産業の現場が迫られる危機の本質と課題を語る。
東海大学熊本キャンパス長の木之内均氏は、日本の品種改良や技術体系は、これまで冷害対策が主流だったが、これからは熱帯研究機関の研究が大切になったと説き、農業生産の現場で起きている危機をレポート。
新潟大学農学部の山崎将紀教授と伊藤亮司助教は、災害級の猛暑に見舞われている全国一の米産地・新潟県の最新状況を報告。同県では暑さに強い品種開発や栽培管理技術の確立が官民挙げて進められている。恒常化する気候変動下の米作り・販売・流通の課題とは。
これらに加え、農林水産省の「地球温暖化影響調査レポート」の概要紹介、および気候変動の海洋生態系や水産資源への影響と対策について、国際捕鯨委員会日本代表代理などを務めた生態系総合研究所代表理事の小松正之氏による特別報告も収録。