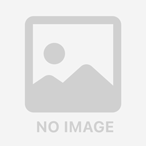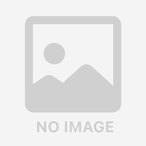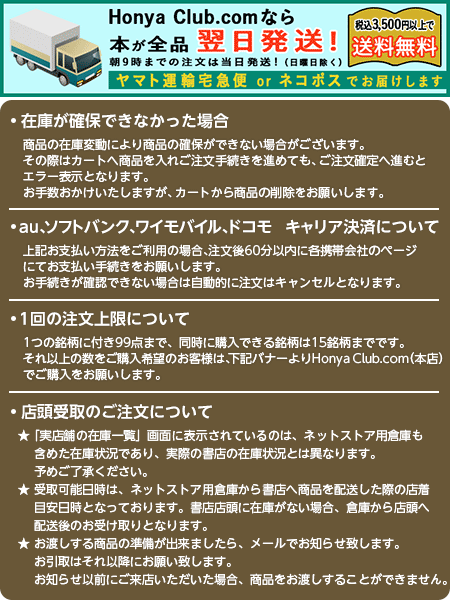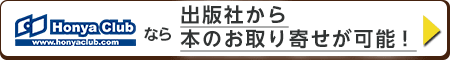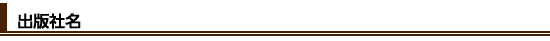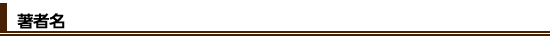翌日発送・一九六八年と宗教/栗田英彦
5,500
出版社名:人文書院
著者名:栗田英彦
発行年月:2025年01月
キーワード:センキュウヒャクロクジュウハチネン ト シュウキョウ、クリタ,ヒデヒコ
著者名:栗田英彦
発行年月:2025年01月
キーワード:センキュウヒャクロクジュウハチネン ト シュウキョウ、クリタ,ヒデヒコ
内容情報
「一九六八年の革命」と「宗教的なもの」は、いかに関係を取り結んだか。
近代宗教史研究と社会運動史研究の架橋により、既存の枠組みでは捉えきれない六八年の運動の秘められた可能性を問う画期的共同研究。時代を牽引したイデオローグが見せたスピリチュアルなものやオカルトへの接近、そして宗教者たちの闘争、それらが持つ意味は何だったのか。
「近年、フランス現代思想やポストコロニアル批評の代表的論者たちが、「宗教の回帰」に至っている。いずれもポストモダニズムのアポリア(例えば脱構築と批判主体のジレンマ)の徹底あるいは超克として、各々の歴史的伝統に立ち返って「宗教」や「霊性」に着目する点に共通性がある。これと相似したことが、日本の〈一九六八年〉以後でも起こっていたのではないか。だが、それが「革命」の具体的な「形式」の問題であるならば、単にアナロジーのみで理解して事足りるわけにはいかない。本書はこのことをポストモダニズムの動向の類比や適用ではなく、〈一九六八年〉の具体的な事例から検討しようとしているのである。」(本書より)
◎目次
序章 「近代主義を超えて」を超えて(栗田英彦)
第I部 一九六八年を捉え直す――芸術宗教・死者・ファシズム
第一章 安保・天皇制・万国博(〓秀実)
第二章 高橋和巳の全共闘運動と一九六八年前後――未成へと向かう臨死者の眼(川村邦光)
第三章 橋川文三の「超国家主義」研究と折口信夫―─「ファシズムと異端神道」論・再考のために(斎藤英喜 )
第II部 一九六八年から新宗教・ニューエイジ運動へ
第四章 神々の乱舞―─一九六八年革命と「民衆宗教」観の変遷(武田崇元)
第五章 一九六八年の身体―─津村喬における気功・太極拳(鎌倉祥太郎)
第六章 革命的抵抗の技術と霊術――戸坂潤・田中吉六・太田竜(栗田英彦)
第III部 一九六八年の宗教――キリスト教から考える
第七章 東大闘争における無教会運動の活動とその背景(エイヴリ・モロー)
第八章 観念と現実のはざま――─ 田川建三における大学闘争と宗教批判(村山由美)
第九章 日本基督教団の「一九六八年」――万博をめぐる闘争から(塩野谷恭輔)
終章――もうひとつの全共闘以後(栗田英彦)