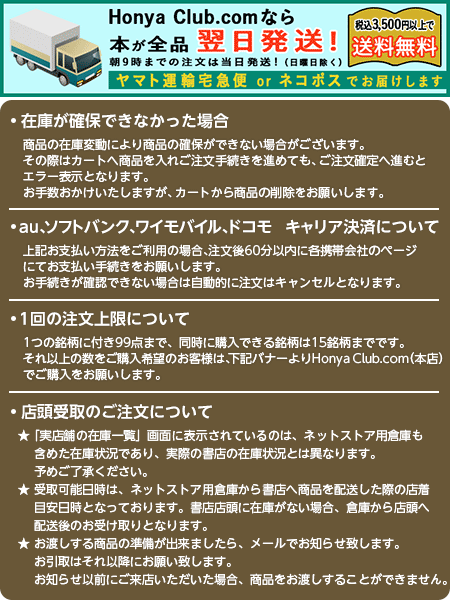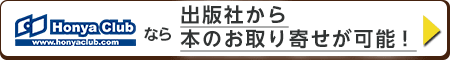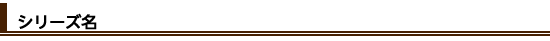翌日発送・認知症は病気ではない/奥野修司
1,166
出版社名:文藝春秋
著者名:奥野修司
シリーズ名:文春新書
発行年月:2024年10月
キーワード:ニンチショウ ワ ビョウキ デワ ナイ、オクノ,シュウジ
著者名:奥野修司
シリーズ名:文春新書
発行年月:2024年10月
キーワード:ニンチショウ ワ ビョウキ デワ ナイ、オクノ,シュウジ
内容情報
政府推計によると、2025年には認知症者の数は約700万人となり、65歳以上の人の約20%が認知症だという。
いまの時代、認知症と宣告されることほど避けたいものはない。
それは「認知症になれば、何も分からなくなる」という思いこみがあるからだ。
長年、認知症当事者を多く取材してきた著者のノンフィクション作家、奥野修司氏は、そうした古い認知症観を捨てなくてはならないと説く。
認知症の人も私たちと同じような感情を持っており、楽しければ笑い、傷つけられたら悲しむし、怒る。
そして多くの当事者が、記憶が失われていくことにおびえている。
そもそも、認知症の約6割、80歳以上に限れば8〜9割を占める「アルツハイマー型認知症」は病気なのか?
老年精神医学の権威、東京大学名誉教授の松下正明氏は「正常加齢者とアルツハイマー型認知症者の脳に質的な差異はなく、加齢と連続した状態とみなしたほうがいい」という。
つまりアルツハイマー型認知症とは、一部の人だけが発症する「病気」ではなく、脳の老化現象なのだ。
老化は誰も避けられないし、記憶力や判断力、実行能力といった認知機能が低下していくのは自然なこと。
しかし、その心や人格まで失われることはない
そうした認識が多くの人に広がっていけば、認知症になってもつらい思いをしなくなるだろう。
大事なことは、家族や地域が力を合わせて支え、認知症になっても生きていける社会を作ること。
認知症の人を介護する家族を悩まるのは、暴言・暴行や徘徊(はいかい)、妄想といった「周辺症状」だ。
本書では、専門家の助言を得て、家族が接し方、考え方を変えたことで、周辺症状が改善した例を紹介する。
また、認知症対策の先進地域の事例を通じて、地域で認知症の人たちを支えている事例も紹介。
認知症に対する考え方を大きく変える一冊だ。