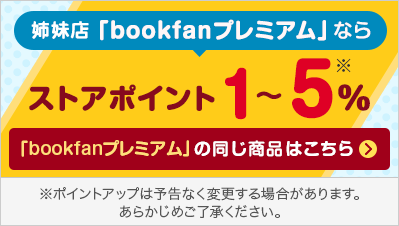句あるべくも 漱石俳句撰/鳥井正晴
3,080
著:鳥井正晴
出版社:和泉書院
発売日:2014年12月
キーワード:句あるべくも漱石俳句撰鳥井正晴 くあるべくもそうせきはいくせん クアルベクモソウセキハイクセン とりい まさはる トリイ マサハル
出版社:和泉書院
発売日:2014年12月
キーワード:句あるべくも漱石俳句撰鳥井正晴 くあるべくもそうせきはいくせん クアルベクモソウセキハイクセン とりい まさはる トリイ マサハル


漢詩と俳句を抜きにして、漱石は語れないだろう。漱石は、「詩」を商品化しなかった。漱石詩は、原稿料と無縁な営みであった。ために己(おの)が胸中を真率に詠い上げる。期間的にも(50年の生涯の)、小説が5分の1に対し、漢詩・俳句は5分の3の期間に及ぶ。数量的にも(短詩形であるが)、漢詩200余首、俳句2500余句と圧倒的に多い。
本書は、本質のリンクする二句を軸に、漱石俳句を論じた学術的エッセイ集。鎌倉漱石の會の会報「門」に12回にわたって連載された。
本書の最大の特色(慧眼)は、二句の選択(合計24句)の妙にある。選択された二句を見れば、苟も文学的感受性(の持ち主)は、何かを感じ、納得するはずである。
二句のみならず、他の句との小説との漢詩との書簡との、その他漱石の諸々の事項との内的関連を閲した縦横の叙述に、漱石文学の全容が彷彿するだろう。
誰か漱石文学の故郷を想わざらん。漱石の直截の声である「俳句」の命題を確かめた、著者渾身の書。
なお、書名の由来となった「句あるべくも花なき国に客となり」は、
本書の最初に取り上げられている。この句は、明治35 年4 月にイギリス留学中だった漱石が渡辺伝右衛門に宛てた手紙に添えられていた。「近代文明の中心都市・倫敦にあっても、漱石は俳句を無下に手放してはいない」(本書6頁)。
※本データはこの商品が発売された時点の情報です。