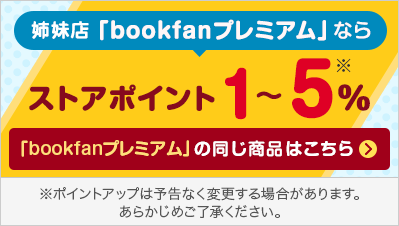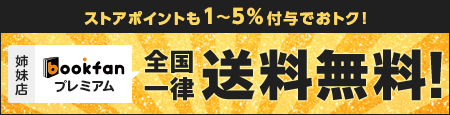コンクリート構造学/宇治公隆
3,410
著:宇治公隆
出版社:コロナ社
発売日:2025年03月
シリーズ名等:土木・環境系コアテキストシリーズ B−3
キーワード:コンクリート構造学宇治公隆 こんくりーとこうぞうがくどぼくかんきようけいこあて コンクリートコウゾウガクドボクカンキヨウケイコアテ うじ きみたか ウジ キミタカ
出版社:コロナ社
発売日:2025年03月
シリーズ名等:土木・環境系コアテキストシリーズ B−3
キーワード:コンクリート構造学宇治公隆 こんくりーとこうぞうがくどぼくかんきようけいこあて コンクリートコウゾウガクドボクカンキヨウケイコアテ うじ きみたか ウジ キミタカ


【読者対象】
想定する読者は、大学や高専など学校でコンクリート構造を勉強し、これから社会に巣立っていく学生はもとより、既に社会に出て建設分野で活躍している若手の技術者で、コンクリート構造に関する基礎をしっかり習得しようという意欲・熱意を持った人たちです。
本書では、コンクリート部材をどういう手順でどう設計したらよいかについて記述していますが、設計と施工は相互に関連しており、設計者のみならず施工を担当している実務者にも役立つよう、記載内容を工夫しています。
【書籍の特徴】
近年では、計算機の利用により、設計プログラムに設計条件を入力すると計算結果が出てくることも多々あり便利になりました。しかし、計算過程もよく分からないブラックボックスの状態となり、計算機任せになってしまいがちで、計算結果の妥当性を判断できない懸念があるとの声も聞きます。
本書は、コンクリート構造物の設計における力学的原理や計算の流れを理解し、合わせて、一般構造細目などの順守すべき決まり事についての基本的な知識を身につけて貰うことを目的としています。
現在、合理的・経済的設計を目指して安全係数を数種類考慮する限界状態設計法が主流となってきていますが、これまで計算の単純化を目的に、材料または荷重に対する安全係数1種類のみ考慮する許容応力度設計法や終局強度設計法が長年活用され、膨大な数の構造物が構築・供用されてきました。そこで、設計法の変遷をも理解するため、それら3種類の設計法の長所や短所を明確にした上で、それぞれの設計法を紹介しています。なお基本的には、どの設計法も力の釣合いをもとに安全性を判断する点において大きな相違は無く、安全率をどこに見込むかの違いともいえるので、その点を理解して貰いたいと思っています。
【学習の対象範囲】
本書は全13章の構成とし、設計において代表的な曲げを受ける部材ならびにせん断力を受ける部材のほか、ねじりや軸圧縮力、繰返し荷重を受ける部材、さらにはプレストレストコンクリートの基本まで勉強できるようにしており、コンクリート構造物に関する設計上想定される項目をほぼ網羅しています。
また、各章での記載内容の理解度を高めるため、それぞれにおいて例題と演習問題を配置しており、本書を通して、コンクリート構造物の設計における基本的な考え方、安全性、使用性、耐久性等の照査手法をしっかり習得できるようにしています。
【著者からのメッセージ】
主として、学校での授業に活用して頂くことを想定していますが、さらには、社会に出てからコンクリート構造物の設計・施工に携わった際にも、設計や施工の業務における参考書として本書を活用して頂ければ有難いです。
【キーワード】
コンクリート構造物の設計、安全性、使用性、限界状態設計法、許容応力度設計法、終局強度設計法
※本データはこの商品が発売された時点の情報です。